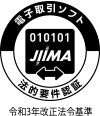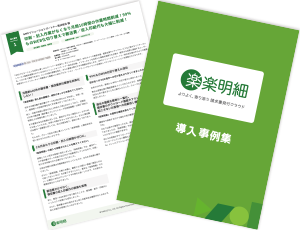領収書を電子化する際に守るべきルールとは?法的効力や注意点

これまで紙で管理していた領収書を電子化する場合、どのようなルールを守ればよいのかよくわからないという方は多いかもしれません。
電子化に際しては、法律上の決まりを守り、正しく発行・保管することが求められます。
この記事では、領収書の電子化に際して知っておきたいルールや注意点、法的効力についての情報などをご紹介します。細かい規定を理解して、要件を満たすオペレーションを構築してください。
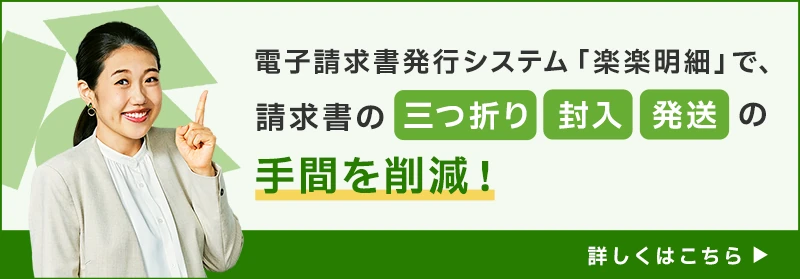
この記事の目次
そもそも電子化した領収書は法的に有効?
電子化した領収書の扱いや効力は紙の書類と変わらず、法的に有効とされています。これは領収書以外の書類についても同様で、納品書や請求書、見積書、支払明細書などを電子データ化しても法律上の有効性があるといわれています。
電子化した書類を保管する際には、電子帳簿保存法の要件に則ることが求められます。つまり発行側でも、控えを保管する場合は電子帳簿保存法に則って管理する必要があるのです。電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電磁的記録として保存することを認めた法律です。受領した領収書や、発行した領収書の控えを電子データとして保存する場合は、法律上の要件を守る必要があります。データの信頼性を担保するために必要とされるいくつかのルールを確認し、所定の方法で保存しましょう。
関連記事:「PDF化した領収書の有効性は?PDFで発行するメリットや注意点・発行方法について解説」
電子化された領収書を保管する際に守るべき主なルール
電子帳簿保存法では3つの保存区分が設けられており、それぞれ異なるルール(要件)が決められています。領収書を電子保存する場合は、電子帳簿保存法にて定められた決まりを守ることが重要です。以下では、電子領収書や控えを保管する際、遵守すべき具体的なルールを解説します。
ルール➀ 訂正・削除の履歴がわかるようにする
電子帳簿保存法の要件の一つに「真実性の確保」があります。データが不正に改ざんされておらず、適切に保管されていることを証明するために必要な要件です。
真実性の要件を満たすための方法の一つに「タイムスタンプ」の付与があります。付与することで、書類が特定の日時に存在していたことを確かめられるようになるのです。
ただし、書類の訂正・削除履歴をたどれるシステムを活用していれば、履歴によってデータに不正な改ざんがないことをば証明できるので、このタイムスタンプは不要になります。
領収書の電子化を推進する際は、このようなシステムの導入も検討することがおすすめです。
また、領収書のタイムスタンプ付与に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。タイムスタンプの基礎知識や付与が必要とされる状況、注意点などを紹介しているため、ぜひ参考にご覧ください。
関連記事:「領収書を電子化する際にタイムスタンプは必要?仕組みや運用のポイント」
ルール➁ データが検索しやすいように保管する
電子帳簿保存法では「可視性の確保」の要件を満たすことも求められます。税務調査が入り、税務職員から特定の書類を提出するよう求められた場合、速やかに検索して発見できる状態にしておく必要があるのです。
取引先・取引年月日・取引金額などの情報で検索できるように整理しておきましょう。決まった項目で検索できるようにしておけば、社内における書類管理の業務効率化や、従業員の負担軽減にもつながります。 その際は、専用システムに搭載された検索機能を活用することで、検索性を高める方法もおすすめです。
紙の領収書と同様の期間保存する
領収書には法律で定められた保存期間があります。電子化した領収書も、紙の領収書と同じ期間保存しなければなりません。
| 事業種の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 法人 | 原則7年間 |
| 個人事業主(青色申告) | 原則7年間 |
| 個人事業主(白色申告) | 原則5年間 |
法人の場合は原則として7年間の保存が義務付けられています。領収書の発行日から数えるのではなく、「事業年度の確定申告書提出期限の翌日より7年間」とされています。個人事業主の場合、青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間の保存義務があります。インボイス対応の領収書の場合、法人・個人事業主ともに7年間の保存が必要です。
関連記事:「領収書の管理・保管方法は?法律的に有効な管理方法や電子化によるメリットを徹底解説 」
領収書を電子化する際のポイント・注意点
領収書電子化を進めるにあたっては、保管のルールや推奨されるファイル形式などを事前に確かめておくことが大切です。以下では、電子化に際してのポイントや注意点を解説します。
電子データで受領した領収書は電子データのまま保管する
電子データの領収書をシステム上でダウンロードしたり、電子メールで受け取ったりした場合は、電子データのままで保存しなければなりません。複合機やプリンターなどで紙に出力して保存するのは、法律上不可とされています。領収書を紙で一元管理したい企業は注意が必要です。今後の業務効率を考えると、ペーパーレス化を進めて電子データによる管理に切り替えるのが望ましいでしょう。
なお、上記のルールは受領した領収書に適用されるものです。2024年時点では、発行者側についての制限はありません。
推奨されるファイル形式はPDF
電子領収書を発行・保管する際は、セキュリティ上の観点からPDF形式で扱うのがおすすめです。領収書はWordやExcelなどを使って作成することも可能ですが、内容を簡単に書き換えられるのが問題です。改ざんのリスクを軽減するため、PDFを利用したほうがよいでしょう。
領収書の電子化に関する申請は特に不要
領収書を電子データに切り替える場合、税務署への申請は必要ありません。法令に従って電子保存できる準備が整っていれば、すぐに運用をスタートできます。
かつては税務署長の事前承認制度が設けられており、適用前の申請・承認が必須とされていました。2022年の電子帳簿保存法改正において要件が緩和された結果、事前申請・承認は不要となっています。
なお、過去分の重要書類をスキャナ保存する場合は届け出が必要となります。詳しくは国税庁のサイトでご確認ください。
参考:国税庁HP「A1-49、C1-73、H4-4国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出(過去分重要書類) 」
領収書電子化のルールを守るために専用システムの導入を検討しましょう
領収書の電子化に関するルールや、守るべきポイント、注意点などを解説しました。領収書を電子化する場合は、発行側・受領側ともに電子帳簿保存法によって定められたルールを守らなければいけません。
しかし、書類一つひとつをチェックして、複雑な要件を満たすように管理するのは大変手間がかかります。ルールを守りながら手間なく電子領収書を発行・保管するには、法律に対応した専用のシステムを取り入れるのがおすすめです。
電子領収書を発行するシステムをお探しの際は、「楽楽明細」をご検討ください。「楽楽明細」は領収書だけではなく、請求書や検収書、納品書、見積書、支払明細書など、さまざまな帳票発行に対応したクラウド型の電子帳票発行システムです。主なメリットは以下の通りです。
➀ 電子帳簿保存法を守って領収書を電子化できる
「楽楽明細」は電子帳簿保存法やインボイス制度などの法律に対応しており、要件を満たして帳票を発行できます。書類ごとに個別で要件をチェックし、対処する手間がかかりません。法的ルールを守りながら容易に領収書の電子発行を実現できるのが大きなメリットです。
➁ 領収書発行・管理のコスト削減を実現できる
「楽楽明細」の導入で電子化を進めると、さまざまなコストの削減につながります。例えば、紙の書類であれば印刷代や用紙代などが必要ですが、電子データであれば費用は生じません。印刷・封入・発送作業をなくせるため、人件費削減にも役立ちます。また、電子文書として発行した領収書の場合は印紙税が課税されません。収入印紙代を削減できるのも魅力です。
➂ 丁寧なサポートでスムーズに電子化を推進できる
電子化が可能なシステムを取り入れたいものの、導入・運用に不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。「楽楽明細」では、お客様ごとに適切な運用方法を提案し、丁寧な導入支援を実施しています。運用開始後もしっかりとサポートするため、安心してご利用ください。
詳しい機能や料金について気になるときは、ぜひ以下のページからお気軽にお問い合わせください。
【無料】3分でわかる!電子請求書発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
関連するコラム
- 記事執筆者紹介
- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部
「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


関連サービスのご紹介
「楽楽明細」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。