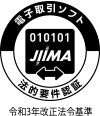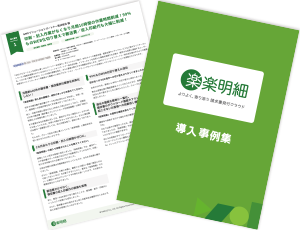納品書の電子化は義務化されている?デジタル化を進めるメリットとは

昨今は多くの企業が納品書をはじめとした書類の電子化に取り組んでいます。そんなビジネスシーンの現状を見て「納品書の電子化は義務化されているのか?」と気になった担当者の方もいるのではないでしょうか。
2024年11月現在、納品書を電子で発行する義務はありません。ただし、納品書のデータ保存に関しては一部義務化されている部分があるため、今後の正確な処理のためにも確認しておきましょう。
この記事では、納品書の電子化に関して経理担当者の方が理解しておきたい基礎知識を解説します。また、電子化を進めるメリットにも触れるため、業務効率の課題を感じているときはぜひ参考にしてみてください。
納品書の電子化の可否については、以下の関連記事でも解説しています。電子化する注意点にも触れているため、こちらも参考にしてみてください。
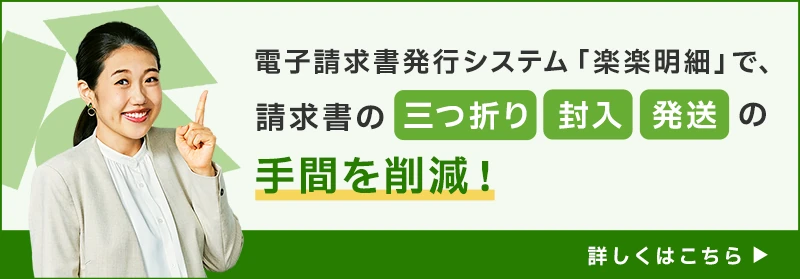
この記事の目次
納品書の電子化は義務化されている?
2024年11月現在、「納品書を電子で“発行”する義務」はありません。そのため、現状の業務フローで納品書の発行が電子化されていなくても、法律による罰則を心配する必要はないといえます。
ただし、納品書を電子データとして受け取った場合は、電子帳簿保存法において「納品書を電子データのまま保存する義務」があります。法改正にともない、2022年から受領した電子納品書を電子データのままで保存することが義務づけられました。その際、電子納品書は以下の要件を満たして保存する必要があります。
- 改ざん防止の措置を取ること
- 「日付」「金額」「取引先」の条件で検索できる状態にすること
- 社内にディスプレイやプリンターを備え付けること
参考:国税庁「電子取引関係」
義務化されている納品書の電子保存を怠ると…?
前述した通り、改正電子帳簿保存法では、電子データで受け取った納品書を電子データのまま保存することが義務づけられています。それでは、もし納品書の保存義務を怠ってしまったら、企業はどのようなペナルティを課されるのでしょうか。
電子帳簿保存法のルールに違反すると、青色申告の取り消しや、悪質な不正に対する追徴課税などのペナルティを課される可能性があります。さらには、会社法においても国税関係帳簿書類を適切に保存していないと見なされ、罰金を科される可能性が考えられるでしょう。
そもそも納品書は、国税関係書類の中でも「取引関係書類」に該当します。企業の取引に関する情報を証明する重要書類であるため、企業側は改ざんや偽造のリスクに備えて、適切な方法で対象書類を保管しなければなりません。納品書を電子化する際は、法律で決められた保管方法のルールを守りましょう。
参考:国税庁「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」
納品書の電子化を進めるメリット・デメリット
納品書の電子化を検討している経理担当者の方も多いでしょう。ここでは、納品書の電子化を進めるメリット・デメリットを解説します。
メリット
➀業務効率化を図れる
納品書を電子で発行すると、書類の作成・発行にかかる時間と手間を短縮できます。専用システムを活用すれば納品書発行を自動化できるので、データ入力・三つ折り・封入・郵送といった業務を無くせます。また、原本をファイリングしたり、保管スペースを整理したりする作業は不要です。業務効率化やペーパーレス化を実現できます。
➁コストを削減できる
専用システムで電子化した納品書は、「クラウドサービスからのダウンロード」や「メール送信」などの方法で、取引先とスムーズに授受できます。その際、印刷代や郵送費用がかからないのがメリットです。業務で納品書を発行する枚数が多い事業者ほど、コスト削減の効果が大きいといえるでしょう。2024年10月の郵便料金の値上げを背景に、郵送費用の削減に取り組んでいる企業にも効果的です。
➂検索性が向上する
納品書を電子化して専用システム上で一元管理すると、過去の納品書を検索しやすくなります。検索機能を利用すれば、ファイル名のほか日付・取引金額・取引先といった任意の記載項目で速やかに文書を検索することが可能です。必要なデータを効率的に参照できるようになり、事務処理の大幅なスピードアップが期待できるでしょう。
「楽楽明細」は納品書や請求書など、あらゆる帳票の電子発行が可能!詳しくはこちら>>>
デメリット
➀一定のコストがかかる
納品書を電子化するために専用システムを導入する場合、初期費用やランニングコストが発生します。また、従来の納品書発行のオペレーションをシステムに合わせて再構築する手間がかかる点にも留意しましょう。ただし、一般的にはシステム導入後に経理業務が大幅に効率化され、結果としてコストメリットを得られるケースが多くなっています。
➁場合によっては二重の手間がかかる
紙の納品書を求める取引先への個別対応が発生する場合、現場の担当者には複数のオペレーションを維持する負担が生じます。取引先が一社でも書面のやりとりを希望する場合、発行側では「紙の納品書」と「電子納品書」の2種類の対応が必要になるのです。
専用システムを導入すると上記のようなデメリットがあるものの、基本的にはメリットが大きく、運用を続けることによって業務効率化やコスト削減の効果を期待できます。費用対効果を考慮して電子化するのがおすすめです。
納品書を電子化する方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事も併せてお読みください。
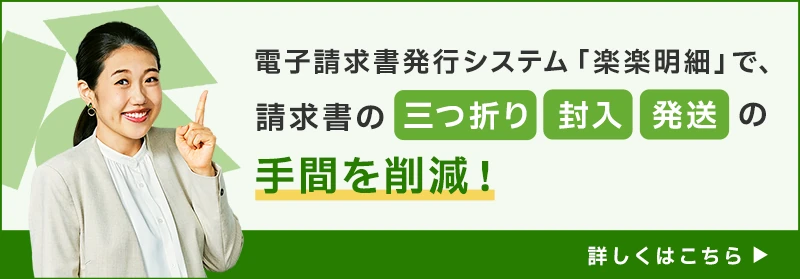
納品書を効率的に電子化する方法
納品書は、表計算ソフトの「エクセル(Excel)」を使って発行することも可能です。ただし、効率的に電子化を推進したい場合は、専用システムの導入をおすすめします。
エクセルはすでに業務で利用している企業が多いので、容易に電子納品書を作成しやすいといえます。一方で、納品書に項目や数量などを入力する際は一つひとつ手入力が必要で、手間がかかるほか人為的なミスが懸念されます。また、エクセルでは承認フローを電子化したり、情報を一元管理したりできないので、根本的な効率化はしにくいといえるでしょう。
それに対して、専用システムは事前に登録したデータをもとに納品書を自動的に発行できます。簡単に書類を作成でき、自動化により手入力の手間やミスを削減できるのが魅力です。さらに、システムは納品書以外の幅広い書類発行や、承認フローの電子化にも対応しています。業務フロー全体を効率化して、課題を解決へ導くことが可能です。
こうした特徴から、専用システムは導入効果が高く、一定のコストをかけても導入後に採算が取れるケースが多くなっています。納品書を効率的に電子化するソリューションをお探しなら、システム導入をご検討ください。
関連記事:「納品書を自動作成する方法|エクセル・システムどちらが効果的?」
納品書を電子化するならシステム導入がおすすめ!
ここまで、納品書の電子化に関する法的なルールを解説しました。2024年11月現在、納品書を電子的に発行する義務はありません。ただし、電子データで受領した納品書を電子データのまま保存することは義務づけられています。
一方で、納品書の発行側についても今後の法改正の動きをチェックすることが重要です。近年は帳票の電子保存にともない、発行する書類も併せて電子化を進める企業が多くなっています。発行する帳票の電子化を進める場合は専用システムを導入するとよいでしょう。その際は、数あるシステムの中でも現場での使いやすさを重視した「楽楽明細」がおすすめです。
ここからは「楽楽明細」の魅力をいくつか解説します。
魅力➀ レイアウトの柔軟性が高い
納品書などに表⽰させる項⽬・位置などをご希望通りに作成できるため、既存の納品書デザインをほぼそのまま再現できます。納品書以外に見積書・注文書・検収書・請求書・領収書などの発行にも対応可能です。
魅力➁ シンプルな画面設計
画面は帳票発行に特化したシンプルな設計です。簡単に理解しやすく、直感的に操作できます。初めてシステムを利用する方でも安心です。
魅力➂ 納品書の送付方法を取引先に応じて選べる
納品書の送付方法は、取引先に応じて「WEBからダウンロード」「メール添付」「郵送代行」「FAX」などから選択できます。電子と紙の両方のオペレーションに対応可能です。
魅力➃ 導入前後のサポート体制が充実している
導入前後のサポートが手厚く、疑問や不安を速やかに解消できます。導入支援はもちろん、運用開始後も提案やフォローを行い、丁寧なサポートを提供いたします。
「楽楽明細」の詳細は無料の資料でご紹介していますので、以下のページからどうぞお気軽にお問い合わせください。
【無料】3分でわかる!電子請求書発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
関連するコラム
- 記事執筆者紹介
- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部
「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


関連サービスのご紹介
「楽楽明細」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。