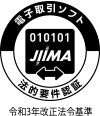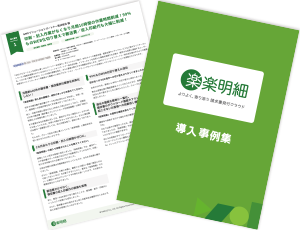【完全版】適格請求書等保存方式とは?その仕組みと変更点を徹底解説!

適格請求書等保存方式とは
適格請求書保存方式は、令和5年10月1日から導入される制度です。令和元年10月1日から適応となった、複数税率に対応する消費税の仕入税額控除の方式として新たに導入されます。
適格請求書とは?
「適格請求書」とは、通常の請求書とどのような違いがあるのでしょうか。適格請求書はインボイス(invoice)とも呼ばれ、「販売側が購入側に対して適正な税率、消費税額が適応されていることを伝えるための書類」です。現在でも活用されている「納品書」、あるいは「請求書」といった証憑書類に分類される書類となります。
また、事業運営にあたり仕入する商品の消費税額を差し引くことができる「仕入税額控除」を受けるためには、適格請求書を作成・保存することが要件です。
適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書を発行するためには、「適格請求書発行事業者登録制度」の申請・登録が必要です。申請を行わない限り適格請求書を発行できず、尚且つ消費税を納める義務がある課税事業者でなければ、登録することはできないため注意が必要となります。
【無料】3分でわかる!請求書発行システム楽楽明細資料はこちら>>>
適格請求書等保存方式の形式
適格請求書等保存方式に適応した請求書の形式は、どのようなものなのでしょうか。下記を参考に、必要事項や形式をご説明しましょう。
適格請求書等保存方式に適応した請求書
1 ○年○月○日
2 ご請求書
3 ○○○御中
4 企業名・連絡先
5 事業者番号○○-○○
6 総請求額 ¥○○○,○○○(税込)
| 7令和○年○月○日 ※お米30Kg ○○,○○○円 |
| 炊飯器 ○○,○○○円 |
| 茶碗 ○○○円 |
| ※ふりかけ ○○○円 |
| 8 合計 ○○○,○○○円 |
9(10%対象 ○○,○○○円 消費税○,○○○円)
10(8%対象 ○○,○○○円 消費税○,○○○円)
11 ※印は軽減税率(8%)適応品
※実際に請求書作成する場合には、上記記載に振り分けられた番号は必要ありません。
適格請求書等保存方式に適応した請求書の解説
1.日付
書類左側に発行日付を必ず記載しましょう。
2.書類タイトル
書類上段には一目で何の書類か分かるように、書類タイトル「ご請求書」と記載しましょう。
3.宛名
請求書を送付する相手先の企業名や氏名を記載しましょう。
4.発行企業名
請求書を発行しる企業名や住所、電話番号、担当者名などを記載しましょう。
5.事業者番号
事業者番号を記載しましょう。
6.総請求額
小計、消費税額を合計した総合計額を記載しましょう。
7.内訳(日付)
請求に対する内訳、日付を記載しましょう。
8.合計と消費税
単価合計と消費税をそれぞれ記載しましょう。
9.消費税10%対象合計金額と税額
消費税10%対象商品の合計金額と税額を記載しましょう。
10.消費税8%対象合計金額と税額
消費税8%対象商品の合計金額と税額を記載しましょう。
11.軽減税率対象商品
※や○などの印を決め、軽減税率対象商品と消費税10%対象商品の区別をしましょう。
【無料】3分でわかる!請求書発行システム楽楽明細資料はこちら>>>
軽減税率対象品目
軽減税率の対象となる品目は、主に酒類を除く生活に必要となる飲食料品と、継続購買となる新聞等です。また、飲食料品であっても外食の場合にはテイクアウト飲食料品が軽減税率対象となり8%、イートインコーナーや店内で飲食をする場合には10%となります。取り扱う品目が軽減税率対象品目であるか、そうでないかをしっかりと把握して対応するようにしましょう。
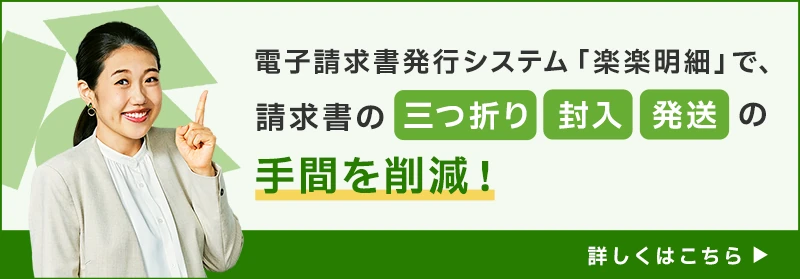
適格請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式の違い
適格請求書等保存方式が適応される、令和元年10月1日から令和5年9月30日まで適応される請求書の形式が区分記載請求書保存方式です。
| 請求書保存方式 | ||
| ~令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日~令和5年9月30日 | 令和5年10月1日~ |
| 請求書等保存方式 | 区分記載請求書保存方式 | 適格請求書保存方式 |
令和元年9月30日まで適応の請求書等保存方式は、長年活用されている馴染みのある形式です。しかし、令和元年10月1日~令和5年9月30日まで適応される区分記載請求書と令和5年10月1日より適応となる適格請求書保存方式では、それぞれ内容が少しずつ異なります。
以下は、各請求書を作成するにあたって必要となる項目です。区分記載請求書保存方式と適格請求書保存方式の違いは「税率毎に区分した対価の合計額とその税率」と「税率毎に区分して合計した消費税額」となり、令和5年9月30日までに、対応準備を行う必要があります。
| 区分記載請求書保存方式と適格請求書保存方式の違い | ||
| 旧 | 令和元年10月1日~令和5年9月30日 | 令和5年10月1日~ |
| 請求書等保存方式 | 区分記載請求書保存方式 | 適格請求書保存方式 |
| 発行側の企業名や氏名 | 発行側の企業名や氏名 | 発行側の企業名や氏名 |
| 取引年月日 | 取引年月日 | 取引年月日 |
| 内訳 | 内訳 | 内訳 |
| 金額 | 金額 | 金額 |
| 宛名 | 宛名 | 宛名 |
| 軽減税率対象商品の旨 | 軽減税率対象商品の旨 | |
| 税率ごとに対価した額 | 税率ごとに対価した額 | |
| 税率毎に区分した対価の合計額とその税率 | ||
| 税率毎に区分して合計した消費税額 | ||
【無料】3分でわかる!請求書発行システム楽楽明細資料はこちら>>>
免税事業者が必要な対策とは
免税事業者とは事業の売上高が1,000万円以下の事業者を指し、納税の義務が免除されます。法人事業者の場合は前々事業年度の課税売上高、個人事業者の場合には前々年の課税売上高を基準に適応されます。
しかし、免税事業主は適格請求書を発行することは認められず、複数税率に対応する消費税の仕入税額控除の適応となりません。そのため、「免税事業者に支払った消費税は控除されない」と嘆く仕入業者も現れると懸念されています。しかし「免税事業主における仕入税額控除の廃止」は段階を踏み、徐々に廃止へと向かって準備期間が設けられています。下記は、免税事業主における仕入税額控除の廃止スケジュールです。
| 期間 | 仕入税額控除率 |
| 現在 ~ 令和5年9月30日まで | 100%控除 |
| 令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日まで | 80%控除 |
| 令和8年10月1日 ~ 令和11年9月30日まで | 50%控除 |
| 令和11年10月1日 ~ | 完全廃止 |
現状のまま免税事業者である場合は、令和11年10月1日より、仕入税額控除が完全に廃止されます。課税事業者からすれば、免税事業者から仕入れるのではなく、仕入税額控除が受けられる事業者から仕入れたいと希望することが自然でしょう。そのため、「免税事業者は取引対象から排除されてしまう恐れ」や、「排除を避けるために価格を低く設定せざるを得ない状況に陥る」ことが懸念されています。
任意で課税事業者になる
上記では、課税売上高が1,000万円以上でなければ課税事業者になれないとご紹介しました。しかし「消費税課税事業者選択届出書」を課税期間前日までに提出することで、任意で課税授業者になれることが可能となります。
ただし、課税事業者の資格がないにもかかわらず任意で課税事業者となった場合、国に消費税を納める義務が発生するため「課税事業者になりたい」という安易な理由だけではリスクがあり、慎重にならなければなりません。
実際に国に納める消費税額は事業者毎に異なり、利益が多い程に納める額も高額になる傾向にあります。そのため、売上事態の金額が少なくても、納税額は高価となるケースも見受けられるでしょう。免税事業者でありながら任意で課税事業者となることをお考えの場合には、どれほどの金額を納めなければならないのか、下記記載の計算式に近々の課税売上高の数字を入替え計算してシミュレーションすることをおすすめします。
| 【 納付する消費税額を算出する計算式 】 |
| ▼ 年間売上高 700万円 / 課税仕入額400万円の場合 |
| 700万円 × 10% - 400万 × 10% = 納税額 30万円 |
▼出典:国税庁ホームページ/[手続名]消費税課税事業者選択届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
今回は、適格請求書等保存方式について詳しくご紹介しました。「楽楽明細」では複雑化する請求書作成の負担を軽減するため、請求書発行から封入、送付までをサポートするサービスを提供しています。「楽楽明細」のご利用をお考えの場合には、お気軽にご相談ください。
【無料】3分でわかる!請求書発行システム楽楽明細資料はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


関連サービスのご紹介
「楽楽明細」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。