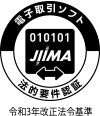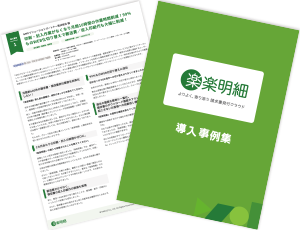納品書のペーパーレス化を進めるメリット・デメリットやよくある疑問

ペーパーレス化とは、これまで紙で行われてきた業務や文書管理をデジタル化し、紙の使用を減らすことです。納品書のペーパーレス化は、納品書を電子化することを指します。書類作成・管理の業務効率やコスト面に課題がある場合は、ぜひペーパーレス化を推進してみてください。
この記事では、納品書のペーパーレス化によって得られる効果や注意点、具体的な方法、実行時に気をつけたいポイントなどを解説します。
納品書の電子化について詳しくは以下の関連記事で解説しています。ペーパーレス化と併せてぜひチェックしてみてください。
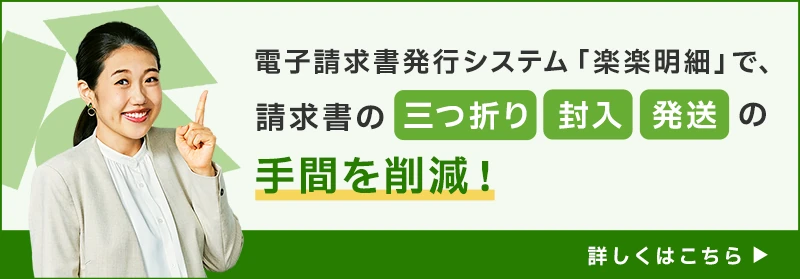
この記事の目次
納品書のペーパーレス化を行うことのメリット・デメリット
納品書のペーパーレス化は企業の抱える課題を解決に導きます。ただし、どのようなデメリットがあるかも把握した上で導入を検討することが大切です。ここでは、納品書のペーパーレス化を行うメリット・デメリットをご紹介します。
メリット
➀コストを削減できる
紙の書類を使わない場合、印刷代や切手代などのコストを削減できます。2024年10月からは、定形郵便物や速達などの郵便料金が値上がりしました。書類を郵送する際の費用が上がったことを受け、コスト削減に頭を悩ませる企業も多いでしょう。納品書をはじめ、さまざまな帳簿書類を電子化すれば、書類の印刷や郵送にかかる費用を節約できます。
関連記事:「【2024年】郵便料金値上げの内容は?企業への影響と対策方法」
➁業務効率化につながる
納品書が紙の場合、印刷や三つ折り、封入、発送といった作業が必要です。ファイリングの手間もかかり、書類保管のために物理的なスペースを確保しなければなりません。書類の数が多いと、担当者の負担も増えてしまいます。
ペーパーレス化した場合、上記の作業がなくなり、業務負荷を軽減することが可能です。
書類保管のために物理的なスペースを確保する必要もなくなります。また、検索してすぐに目的の書類を見つけられるのもメリットです。ファイルなどの備品代や、場所代も減らせるでしょう。
「楽楽明細」は納品書や請求書など、あらゆる帳票の電子発行が可能!詳しくはこちら>>>
デメリット
➀業務フローを再構築する必要がある
これまで紙で書類作成していた場合、ペーパーレス化を進めるためには業務フローを見直す必要があります。承認や捺印などのオペレーションも、電子化に合わせて再構築しなくてはいけません。また、納品書をはじめとする書類の電子化は、電子帳簿保存法に定められた要件に従うことが求められます。法制度の要件を満たすための業務フロー構築が必須です。
➁一定のコストがかかる
ペーパーレス化に際して新規のシステムやツールなどを導入する場合、一定のコストが生じます。導入費用はもちろん、ランニングコストがどの程度かかるのかを確かめておきましょう。また、新しいオペレーションが浸透するまでには時間がかかります。システムの料金だけではなく、従業員への教育コストなども含めて費用対効果を検討するのがポイントです。
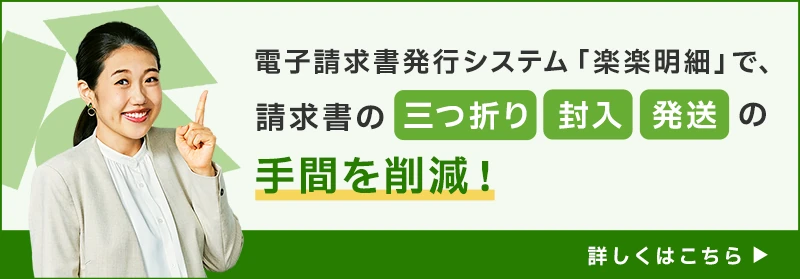
納品書をペーパーレス化する主な方法
納品書のペーパーレス化は、主に「エクセル(Excel)を活用する方法」と「システムを導入する方法」に分けられます。それぞれのメリット・デメリットを比較して、自社に合うほうを選びましょう。
【エクセルを活用する】
・メリット
エクセルは幅広い企業に導入されています。エクセルを利用したペーパーレス化であれば、コストをかけずにスタートしやすいのがメリットです。
・デメリット
エクセルはあくまでも表計算ソフトであり、効率化できる範囲には限界があります。データの手入力が必要であり、人為的なミスが起こるリスクも避けられないでしょう。
【システムを導入する】
・メリット
システムを導入すれば、書類発行の自動化やオンライン上での承認などが実現できます。業務効率化を期待できるのは大きな魅力です。
・デメリット
システムの導入に際しては相応のコストが発生します。希望のサービスを見つけたら見積もりを依頼し、詳細な金額を確かめておくことが大切です。
それぞれ異なるメリット・デメリットがありますが、作業の自動化や効率化を目指すならシステム導入がおすすめです。コストはかかりますが、業務効率化が実現すれば将来的には人件費などのコスト削減につながります。導入費用やランニングコストの採算も取れるでしょう。
関連記事:「請求書を電子化するやり方は主に2つ!データ化の進め方や注意点」
納品書のペーパーレス化を進めるときのポイント
納品書をペーパーレス化する際は、以下のポイントに気をつけましょう。ここでは、ペーパーレス化の推進に際して注意しておきたいことを解説します。
社内や社外へ周知をする
納品書のペーパーレス化が決まったら、社内の人員に周知します。運用フローをスムーズに移行できるよう、事前に従業員向けのマニュアルを用意しておくとよいでしょう。また、取引先の顧客にも電子化の旨を伝えることが重要です。企業によっては電子データではなく、従来のように紙の納品書を求められるケースがあります。この場合は個別での対応が必要です。
関連記事:「請求書の電子化依頼メールの書き方|取引先への伝え方のポイント」
法要件に沿うように電子化をする
納品書をペーパーレス化する際は、電子帳簿保存法を順守しなくてはいけません。電子帳簿保存法では、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引の3つの区分で保存要件が定められています。要件を守らない場合は法律違反となるおそれがあります。
納品書管理の際、一つひとつの要件をチェックしていくのは非常に手間がかかります。法律に関する知識がない場合はそもそものオペレーション設計から間違えてしまうこともあるでしょう。リスクを避けるためにも、電子帳簿保存法の要件に対応したシステムを導入するのもおすすめです。専用システムを活用すれば、法的な要件を満たした社内環境を整備し、納品書をペーパーレス化できます。
セキュリティ体制を整える
ペーパーレス化を実行する場合、情報漏洩などのトラブルについてはしっかりと備えておく必要があります。データにアクセス可能な従業員を制限する、誤送信を避けるためにチェック体制を強化するなど、セキュリティ対策を行いましょう。トラブルが生じた際のオペレーションも事前に決めておくことが大切です。また、電子化した書類はPDFデータとして発行するとよいでしょう。パスワード設定が可能であり、改ざんや流出を防ぎやすくなります。
納品書のペーパーレス化に関するよくある質問
ここでは、納品書のペーパーレス化でよく見られる疑問や、回答をご紹介します。気になる疑問点を解消しておきましょう。
Q1. 納品書の電子化は義務化されている?
2024年の時点では納品書の電子化が義務付けられているわけではないため、紙の書類を使い続けても法律上の問題はありません。ただし、電子データの状態で授受した納品書については、電子データのままで保存する義務があります。例えば、PDFファイルとして受領した納品書を紙に印刷して保存することはできません。
関連記事:「納品書の電子化は義務化されている?デジタル化を進めるメリットとは」
Q2. ペーパーレス化した納品書は法律的に有効?
電子化した納品書も、紙の納品書と変わらずに法的に有効とされています。ただし、電子データは電子帳簿保存法に則った方法で保存しなくてはいけません。保存要件について理解を深めたいときは、ぜひ以下の記事も参考にご覧ください。
参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
Q3. これまで紙で保管していた納品書はどう処理すればいい?
納品書を電子化した場合、紙の原本は破棄して問題ありません。電子化しないのであれば、決められた期間、紙のまま保管しておきましょう。
【納品書の保管期間】
- 法人の場合:基本的に7年間
- 個人事業主の場合:5年間(青色申告の場合は7年間)
なお、スキャナ保存を開始した日以前に作成・受領した納品書(=過去分重要書類)を電子化する場合は申請が必要です。事前に適用届出書を税務署長などへ提出しましょう。
参考:国税庁「A1-49、C1-73、H4-4国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出(過去分重要書類)」
納品書のペーパーレス化で発行・管理業務効率化を実現!
納品書のペーパーレス化によるメリット・デメリットや主な方法、注意点などをご紹介しました。ペーパーレス化を実施すれば、業務効率化やコスト削減につなげることが可能です。便利なシステムを導入して、スムーズに電子化を進めましょう。
納品書をはじめ、帳票の発行・送付をシステム化するなら「楽楽明細」がおすすめです。
魅力➀複数の帳票に対応
納品書はもちろん、領収書や請求書、検収書など、さまざまな帳票を発行できます。柔軟なレイアウトが可能で、現在使用中のフォーマットを再現することもできます。
魅力➁画面設計がシンプルで使いやすい
画面設計がシンプルで使いやすいため、直感的に操作できます。システムの操作に不慣れな方でもスムーズに利用できます。
魅力➂電子帳簿保存法に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度などの各種制度に対応しています。法的な要件を満たして書類を発行・保存できます。
魅力➃導入前後のサポートも充実
導入前後のサポートが充実しているので、不明な点がある場合も速やかに解決できます。初めてのシステム導入でも安心してご利用いただけます。
「楽楽明細」の導入で具体的にどんな効果が得られるのか気になったら、ぜひ以下の導入事例をご覧ください。
「楽楽明細」の詳細は無料の資料でご紹介していますので、以下のページからどうぞお気軽にお問い合わせください。
【無料】3分でわかる!電子請求書発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
関連するコラム
- 記事執筆者紹介
- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部
「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


関連サービスのご紹介
「楽楽明細」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。